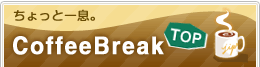ちょっと一言
「驚く土の力」7月号編集後記より
「土と生命の46億年史」(藤井一至,2024年,講談社)を読みました。「土は人間に作れない」「腐食のレシピは土の中の無数の微生物しか知らない」「自然の営みによって1センチメートルの土が作られるのには100〜1000年もかかる」と,「はじめに」記載があり驚きます。
そもそも「土とは岩石が崩壊して生成した砂や粘土と生物遺体に由来する腐食の混合物である」。陸上に植物が上陸する5億年前まで土はなかったことになります。電気を帯びる性質により,粘土が生命誕生に重要な役割を果たしたらしいですね。知りませんでした。
そして藤井さんは,生物の組成が地球の組成と深く結びついていて生物はそれを補充することで生きていけること,人類は土の恵みを利用できたからこそ繁栄したことを語ります。しかし「土は人間に作れない」。人工土壌の研究はうまくいっていません。但し,土壌生成を加速することはできるそうで,例えば,隣の天然林の土を借りてきて荒地にまくのは効果があるようです。
土の重要性に気づく話といえば「奇跡のリンゴ」(石川拓治,2008年,幻冬舎)。これは木村秋則さんによるリンゴ無農薬栽培のノンフィクションです。農薬散布作業により体調不良になる奥様のために,代替品発見に取り組む木村さん。しかし,何年も病害虫大発生を繰り返し,貧窮の中で苦悩します。自死を図ろうとした山中で,彼は見事なリンゴの樹に気づきます。実際それは椎の木だったのですが,何が違うのか。山とリンゴ畑は土が違ったのです。
そして,無農薬を試みて9年目の春に,木村さんのリンゴ畑は再び全ての樹で開花します。そもそも自然に存在しない,品種改良されたリンゴを栽培することと自然の摂理を調整することを木村さんは目指すのです。肥料は化学も有機も与えない,畑に雑草を生やして土を自然の状態に近づける,土に窒素が不足していれば大豆を播く,等。木村さんのリンゴの樹は逞しくなり,台風が来ても倒れず,実を落としません。根は他の畑の樹の2〜3倍の深さに達します。畑の土の微生物の多様性は白神山地並みです。
組織に置き換えると,一人一人をよく見て自然さを損なわず,それでいて全体としては成果を出すよう整えるということでしょうか。多様な才能の葉が茂るといいですよね。
そもそも「土とは岩石が崩壊して生成した砂や粘土と生物遺体に由来する腐食の混合物である」。陸上に植物が上陸する5億年前まで土はなかったことになります。電気を帯びる性質により,粘土が生命誕生に重要な役割を果たしたらしいですね。知りませんでした。
そして藤井さんは,生物の組成が地球の組成と深く結びついていて生物はそれを補充することで生きていけること,人類は土の恵みを利用できたからこそ繁栄したことを語ります。しかし「土は人間に作れない」。人工土壌の研究はうまくいっていません。但し,土壌生成を加速することはできるそうで,例えば,隣の天然林の土を借りてきて荒地にまくのは効果があるようです。
土の重要性に気づく話といえば「奇跡のリンゴ」(石川拓治,2008年,幻冬舎)。これは木村秋則さんによるリンゴ無農薬栽培のノンフィクションです。農薬散布作業により体調不良になる奥様のために,代替品発見に取り組む木村さん。しかし,何年も病害虫大発生を繰り返し,貧窮の中で苦悩します。自死を図ろうとした山中で,彼は見事なリンゴの樹に気づきます。実際それは椎の木だったのですが,何が違うのか。山とリンゴ畑は土が違ったのです。
そして,無農薬を試みて9年目の春に,木村さんのリンゴ畑は再び全ての樹で開花します。そもそも自然に存在しない,品種改良されたリンゴを栽培することと自然の摂理を調整することを木村さんは目指すのです。肥料は化学も有機も与えない,畑に雑草を生やして土を自然の状態に近づける,土に窒素が不足していれば大豆を播く,等。木村さんのリンゴの樹は逞しくなり,台風が来ても倒れず,実を落としません。根は他の畑の樹の2〜3倍の深さに達します。畑の土の微生物の多様性は白神山地並みです。
組織に置き換えると,一人一人をよく見て自然さを損なわず,それでいて全体としては成果を出すよう整えるということでしょうか。多様な才能の葉が茂るといいですよね。
 近くの公園で
近くの公園で
(H.K.)