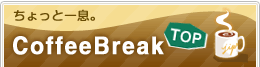新刊書紹介
新刊書紹介
不正競争防止法(事例・判例)第2版
| 編著 | 青山 紘一 著 |
|---|---|
| 出版元 | 経済産業調査会 A5判 870p |
| 発行年月日・価格 | 2010年5月18日発行 8,600円(税別) |
近時,「ブランド」の重要性は知財関係者のみならず,各方で話題に挙がっていますが,「ブランド」における商標の役割は改めて言をまたないところで不正競争防止法,改めて見直すとわずか22条からなるものである。しかし,条文の少なさとは裏腹に非常に広範囲をカバーする内容となっている。さらには懲役刑や罰金刑など,刑事罰まで課されていることを再認識する。外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止まで載っているのは本書を読むまで知らなかった。
また,報道で目にする事件も多く,消費者に直接影響を及ぼす事件に関連することも多いので,法律に疎い者でも直感的に理解しやすい法だと思う。
はしがきでも述べられているように改正が繰り返されており,2002年から実に5度の一部改正が立て続けになされているとのことである。 ネット社会への移行やノウハウ保護など時代の変化に急ぎ対応する必要が根底にあると考える。
本書は事例・判例のタイトルではあるが,前半では不正競争防止法の詳細な解説,立法経緯の説明がなされている。著者の意見も随所に記載されている。各解説の項目ごとに事例が数行ずつにまとめられ,ふんだんに記載されているので具体的でわかりやすい。不正競争防止法概要をつかむには前半部分のみ読んでも良いだろう。とはいえ,前半部分のみでも250ページ超で充実しており,読破するのには覚悟が必要である。必要箇所を拾い読みするのみでも有用な構成となっているので心配は無用だが。
後半,多くの具体的な事例が掲載されている。食肉偽装事件,うさぎのキャラクターに関わる事件,著名ブランドに関わる事件など,どこかで見聞きした覚えのある事件が目白押しである。これらの事例はせいぜい数ページにまとめられているので読むにあたって抵抗もなく,ポイントとなる図や写真も豊富で理解しやすい。 関連する事例を適度に分類しまとめて編集してあるので,気になる事例や項目を理解するには非常に有用だろう。
本書の利用の仕方はいろいろあろう。例えば,ある特定の項目(例えば著名表示冒用行為,営業秘密の不正取得等)に注目して,前半部分のみ読むことだけでも,かなりのことは理解できよう。
ある特定の事例に注目する場合は,まずは注目事例の解説そのものを読み,その項目でまとめられている関連事例も合わせて読めば,いっそう有効と思われる。さらには前半の関連解説部分まで戻って読めばよい。
不正競争防止法で疑問に思うことがあれば,まず本書であたってみてはいかがだろうか。22条の条文も巻末に掲載されている。パラパラとめくるだけでも様々な発見がある。辞書代わりに部署に1冊は欲しい本である。
(会誌広報委員会 A.N.)
新刊書紹介
専門訴訟大系2 知財訴訟
| 編著 | 小山 稔・西口 元 編集代表 久保利 英明・北尾 哲郎 編 |
|---|---|
| 出版元 | 青林書院 A5判 288p |
| 発行年月日・価格 | 2010年5月25日発行 2,800円(税別) |
本書は,長年知財訴訟に携わってきた弁護士の執筆による知財訴訟に関する実務書であり,そのタイトルが示す通り,特許権,実用新案権, 意匠権,商標権からなる,いわゆる産業財産権のみならず,著作権及び不正競争防止法に関する事件も扱った内容となっている。
「第1章 総論」では,知財訴訟の特徴として,専属管轄,差止請求権,産業財産権についての権利無効の抗弁,及び民訴法上の文書提出命令を拡充した文書提出命令がそれぞれ法定されていることについて解説されている。民訴法が適用される知財訴訟ではあるが,訴訟手続において独自の規定が存在することを分かりやすく説明している。
「第2章 各論」では,「Ⅰ 相談・事情聴取と証拠収集」,「Ⅱ 法的解決手段の決定」,「Ⅲ 訴訟提起の段階でなすべきこと」,「Ⅳ 訴訟における主張・立証」,「Ⅴ 訴訟の終了(和解,判決,控訴等)」の順で時系列に沿って解説がなされている。「Ⅰ 相談・事情聴取と証拠収集」では,特に不正競争行為のいずれの類型に該当するかにつき,条文の解説も含め,詳細に記載されている。「Ⅱ 法的解決手段の決定」では,本案訴訟のみならず,仮処分・水際規制,調停・仲裁・和解等の解決手段について解説されている。また,それぞれの解決手段を取った場合のメリット・デメリットが記載されており,解決手段選択の際の良い目安となるものと思われる。知財事件における法的解決手段として,普段あまり接することのない水際規制について,わかりやすく解説すると共に,その手続きの流れをフローチャートで示して解説されており理解の一助となる。「Ⅲ 訴訟提起の段階でなすべきこと」では,技術的事項が争点となる点で他の訴訟類型とは異なる特徴を有しているとして,特許・実用新案を中心に,原告側,被告側の対応について説明されている。さらに,原告の対応として,権利侵害に対する第三者への告知を行う場合につき,当該告知行為が正当な権利行使の一環と認められるかどうかを基準 に判断すべきことが,通説・判例であるとして,判決例を示して解説されている。「Ⅳ 訴訟における主張・立証」では,いわゆる攻撃・防御方法における検討・留意事項が豊富な判例・論文を引用して説明され,「Ⅴ 訴訟の終了(和解,判決,控訴等)」では,近時の知財訴訟の統計的状況を示しており,知財訴訟の約半数が和解によるものであること,また,東京地裁民事第29部においては,終局事件の約60%が原告勝訴見込みのもとでの和解であることが分かる。
本書は,これ一冊で知財訴訟に関連する必要十分な事項を網羅しており,初学者にとっては知財訴訟の理解に,また,実務家にとっては,「かゆいところに手が届く」一冊として実務に役立つものと思われる。
(会誌広報委員会 S.K.)