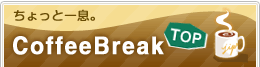新刊書紹介
新刊書紹介
知財・無形資産ガバナンス入門
| 編著 | 知財ガバナンス研究会 菊池 修・山口 裕司 編著 |
|---|---|
| 出版元 | 中央経済社 A5判 460p |
| 発行年月日・価格 | 2024年6月18日発行 5,720円(税込) |
知財・無形資産ガバナンスは,サステナビリティ経営において知的財産や人材などの無形資産を有効活用する経営手法であり,2021年6月のコーポレートガバナンス・コードの改訂を契機にその要請が一層高まっている。
知財・無形資産ガバナンスに関して,以前から疑問に感じていることがあった。それはサステナビリティと収益性の両立は本当に実践可能なのか,という点である。この疑問に対して,本書では,「日本企業の強みである無形資産を活用してイノベーションを創出し,環境・社会のサステナビリティと企業成長を両立させる」という方向性が全体を通して示されている。
一方,業務レベルに目を向けると,知財・無形資産の活用が重要な経営マターになってきている流れは理解できるものの,実際に何をどう実践すれば良いのか分からず,雲を掴む感覚を覚える知財実務者も多いのではなないだろうか。筆者もその一人である。この戸惑いに対しても,戦略策定から統合報告書等での開示に亘り具体的かつ詳細に実践方法が示されている。
個人的には,財務諸表に計上されない知財・無形資産について,投資家がどのように把握しているか,また,どのような開示方法が有効なのかが分かりやすく解説されており,最も得心したところでもある。投資家は時価総額等の財務指標を投資戦略に沿って使い分けている。一口に「投資家」と言っても,アクティブ運用とパッシブ運用に大別され,更にグロース株投資やバリュー株投資等の戦略によって分けられる。知財・無形資産の活用は中長期視点で企業価値向上を目指すものであることから,長期投資家に働きかけることが重要になる。ビジネスモデルにおける「企図する因果パス」のアウトカムとしてROIC(資本効率)およびPER(成長期待)が多用されるのは,正にこの理由であろう。
加えて,長期投資家は保有する知財・無形資産がどのような位置づけで,どのように収益化しているのかについても注目している。この点で有効な手段がIPランドスケープによる戦略開示である。本書ではIPランドスケープのフレームワークや好事例が紹介されており大変参考になる。また,KPI,インプット,アウトプットおよびアウトカムについて,定性的説明および定量的指標が具体的かつ幅広く解説されている。
本書は知財・無形資産ガバナンスの指南書的役割を担っており,知財実務者のみならず,IR,経営企画,事業・技術開発等に所属されている方々にとっても有益な一冊となるだろう。
知財・無形資産ガバナンスに関して,以前から疑問に感じていることがあった。それはサステナビリティと収益性の両立は本当に実践可能なのか,という点である。この疑問に対して,本書では,「日本企業の強みである無形資産を活用してイノベーションを創出し,環境・社会のサステナビリティと企業成長を両立させる」という方向性が全体を通して示されている。
一方,業務レベルに目を向けると,知財・無形資産の活用が重要な経営マターになってきている流れは理解できるものの,実際に何をどう実践すれば良いのか分からず,雲を掴む感覚を覚える知財実務者も多いのではなないだろうか。筆者もその一人である。この戸惑いに対しても,戦略策定から統合報告書等での開示に亘り具体的かつ詳細に実践方法が示されている。
個人的には,財務諸表に計上されない知財・無形資産について,投資家がどのように把握しているか,また,どのような開示方法が有効なのかが分かりやすく解説されており,最も得心したところでもある。投資家は時価総額等の財務指標を投資戦略に沿って使い分けている。一口に「投資家」と言っても,アクティブ運用とパッシブ運用に大別され,更にグロース株投資やバリュー株投資等の戦略によって分けられる。知財・無形資産の活用は中長期視点で企業価値向上を目指すものであることから,長期投資家に働きかけることが重要になる。ビジネスモデルにおける「企図する因果パス」のアウトカムとしてROIC(資本効率)およびPER(成長期待)が多用されるのは,正にこの理由であろう。
加えて,長期投資家は保有する知財・無形資産がどのような位置づけで,どのように収益化しているのかについても注目している。この点で有効な手段がIPランドスケープによる戦略開示である。本書ではIPランドスケープのフレームワークや好事例が紹介されており大変参考になる。また,KPI,インプット,アウトプットおよびアウトカムについて,定性的説明および定量的指標が具体的かつ幅広く解説されている。
本書は知財・無形資産ガバナンスの指南書的役割を担っており,知財実務者のみならず,IR,経営企画,事業・技術開発等に所属されている方々にとっても有益な一冊となるだろう。
(紹介者 会誌広報委員 K.H)