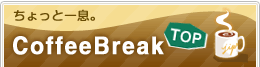新刊書紹介
新刊書紹介
ライセンス契約の理論と実務−新時代ビジネスの知財活用戦略−
| 編著 | 齋藤 浩貴 著 |
|---|---|
| 出版元 | 青林書院 A5判 334p |
| 発行年月日・価格 | 2024年7月発行 4,840円(税込) |
本書は,デジタル著作物,データ,共創,外国企業,標準必須特許(SEP)といった幅広い対象に関するライセンス契約について,実践的なガイダンスを提供するものである。
第1章では,特許/商標/著作権についてのライセンス契約の概要,ライセンス契約と独占禁止法の関係が簡潔に記載されており,初学者に配慮されている。また,ライセンスの内容が争点となった判例も記載されており参考になる。
第2章では,OSSやNFTを例としてデジタル著作物のライセンスが解説されている。OSSで一般的なライセンスを例に挙げ,OSSライセンスに特有の課題(ソースコードの公開義務,OSSを利用した派生物に対するOSSの規定の伝搬性,複数のOSSを組み込んだ製品に対してOSS条項が重畳適用された場合の条項同士の両立性)を述べ,実務上注意すべき点がまとめられている。NFTについては,その仕組みから解説されており,馴染みのない読者にとっても興味を惹かれるものになっている。
第3章では,AIシステムの学習データとして重要度の増すビッグデータを一例として,不競法によるデータ保護,データライセンス契約の概要,プライバシーに関するデータにおいて考慮すべき個人情報保護法について述べられている。特に,2018年の不競法改正で導入された限定提供データについて,要件から不正競争行為の類型まで解説されており,営業秘密による保護よりも不正競争に該当する要件が厳しい点が注意喚起されている。
第4章では,知的財産の創出取引とライセンスとして,共同研究開発,映像作品の制作,システム開発委託のライセンス契約について解説されている。特許権や著作権の関連法令を概説した上で,上述のライセンス契約について考慮すべきポイントが詳述されている。例えば,システム開発委託契約では,2020年に経産省が公表したモデル契約を参照し,契約時に手当すべき事項やリスクについて述べられている。
第5章では,医薬品特許と映画化権の2つを例として,外国企業との英文ライセンス契約における注意点が解説されている。マイルストーン達成毎に支払金発生を規定することでライセンサーの資金的保護を図る手法など,医薬品に限らず,ベンチャー企業との共創を促進する上で,他分野でも大いに参考になると思われる事例が示されている。
第6章では,SEPライセンス交渉の各ステップにおける留意点が,SEPの保有者と実施者の立場から解説されている。特にFRAND条件について,具体的な判例紹介もあり,実務上参考になる。
本書のタイトルの通り,ライセンス契約の理論と実務を体系的に学習できるものと感じた。知財・法務担当の方々に,是非,本書を手元に置いて参考にしていただきたい。
第1章では,特許/商標/著作権についてのライセンス契約の概要,ライセンス契約と独占禁止法の関係が簡潔に記載されており,初学者に配慮されている。また,ライセンスの内容が争点となった判例も記載されており参考になる。
第2章では,OSSやNFTを例としてデジタル著作物のライセンスが解説されている。OSSで一般的なライセンスを例に挙げ,OSSライセンスに特有の課題(ソースコードの公開義務,OSSを利用した派生物に対するOSSの規定の伝搬性,複数のOSSを組み込んだ製品に対してOSS条項が重畳適用された場合の条項同士の両立性)を述べ,実務上注意すべき点がまとめられている。NFTについては,その仕組みから解説されており,馴染みのない読者にとっても興味を惹かれるものになっている。
第3章では,AIシステムの学習データとして重要度の増すビッグデータを一例として,不競法によるデータ保護,データライセンス契約の概要,プライバシーに関するデータにおいて考慮すべき個人情報保護法について述べられている。特に,2018年の不競法改正で導入された限定提供データについて,要件から不正競争行為の類型まで解説されており,営業秘密による保護よりも不正競争に該当する要件が厳しい点が注意喚起されている。
第4章では,知的財産の創出取引とライセンスとして,共同研究開発,映像作品の制作,システム開発委託のライセンス契約について解説されている。特許権や著作権の関連法令を概説した上で,上述のライセンス契約について考慮すべきポイントが詳述されている。例えば,システム開発委託契約では,2020年に経産省が公表したモデル契約を参照し,契約時に手当すべき事項やリスクについて述べられている。
第5章では,医薬品特許と映画化権の2つを例として,外国企業との英文ライセンス契約における注意点が解説されている。マイルストーン達成毎に支払金発生を規定することでライセンサーの資金的保護を図る手法など,医薬品に限らず,ベンチャー企業との共創を促進する上で,他分野でも大いに参考になると思われる事例が示されている。
第6章では,SEPライセンス交渉の各ステップにおける留意点が,SEPの保有者と実施者の立場から解説されている。特にFRAND条件について,具体的な判例紹介もあり,実務上参考になる。
本書のタイトルの通り,ライセンス契約の理論と実務を体系的に学習できるものと感じた。知財・法務担当の方々に,是非,本書を手元に置いて参考にしていただきたい。
(紹介者 会誌広報委員 T.M.)
生成AIと知財・個人情報Q&A
| 編著 | 齋藤浩貴・上村哲史 編著 |
|---|---|
| 出版元 | 商事法務 A5判 288p |
| 発行年月日・価格 | 2024年7月発行 3,300円(税込) |
本書は,生成AI(Generative AI)が引き起こす法的課題に対する実務的な回答を,Q&A形式で提供する書籍である。特に,知的財産や個人情報保護に焦点を当て,生成AI技術が日々進歩する中で,企業や開発者,知財担当者が直面する現実的な問題にどう対応すべきかを解説している。
近年,生成AI技術の進展や国際的な動向を受け,生成AIを巡る法整備の必要性が日本でも活発に議論されており,著作権法や個人情報保護法の改正が大きな焦点となっている。特に,2022年4月に施行された改正個人情報保護法において,個人の権利が拡充され,罰則が強化されたことは記憶に新しい。しかし現時点では生成AIの問題を網羅的に解決できるような法律はなく,知財担当者が実務で疑問を感じる場面もあると思われる。また,本書執筆時点では,生成AIを利用して生成された情報を提供した場合,情報を提供した生成AI利用者及び当該利用者が属する企業がその責任を負うと考えられており,企業はその取り扱いに十分な注意を払う必要がある。この現状を踏まえ本書では,企業が現行法の枠組みの中で生成AIを適切に利用するための指針を示している。
本書では,弁護士23名が,73ものQ&Aを執筆・編集している。第1章の「生成AIとは何か」という基本知識の解説からスタートし,第2章では「生成AIと知的財産権」,第3章では「生成AIと個人情報・プライバシー・肖像権等」,第4章では「その他」として海外の法規制の動向や社内規程について解説している。重点的に解説している生成AIと著作権(Q10〜Q43)だけでなく,AI生成物の特許登録(Q44),AI生成物の意匠登録(Q49),AI生成物の商標登録(Q52)に関する法的問題についても,既存の法律の解釈に関する最新の考え方やガイドラインを示しつつ,現時点での見解を記している。 例えば特許法では,発明者は自然人でなければならないが,創作過程にどの程度関与すれば自然人の発明と認められるのかについての課題は,近年AIによる自律的創作が実現しつつあるとの指摘を踏まえ,現在も整理・検討が進行中とのことである。本書の中で繰り返し「この点の今後の議論が待たれる」,「裁判例の集積が待たれる」,「今後立法による解決が待たれる」とあり,今後議論され,法整備されるべき論点が何であるかを理解する上でも本書は非常に有益だと感じた。
本書は生成AIの急速な普及と法的な変化に対応するために,実務者が必要とする情報をわかりやすく提供している。日本の法整備が検討される中,生成AI技術の利用に関して現状どのような法的リスクが存在し,それをどのように回避するかを解説しており,今後注目すべき論点を認識する上でも,生成AIの利用を考える方にとって必読の一冊と言える。
近年,生成AI技術の進展や国際的な動向を受け,生成AIを巡る法整備の必要性が日本でも活発に議論されており,著作権法や個人情報保護法の改正が大きな焦点となっている。特に,2022年4月に施行された改正個人情報保護法において,個人の権利が拡充され,罰則が強化されたことは記憶に新しい。しかし現時点では生成AIの問題を網羅的に解決できるような法律はなく,知財担当者が実務で疑問を感じる場面もあると思われる。また,本書執筆時点では,生成AIを利用して生成された情報を提供した場合,情報を提供した生成AI利用者及び当該利用者が属する企業がその責任を負うと考えられており,企業はその取り扱いに十分な注意を払う必要がある。この現状を踏まえ本書では,企業が現行法の枠組みの中で生成AIを適切に利用するための指針を示している。
本書では,弁護士23名が,73ものQ&Aを執筆・編集している。第1章の「生成AIとは何か」という基本知識の解説からスタートし,第2章では「生成AIと知的財産権」,第3章では「生成AIと個人情報・プライバシー・肖像権等」,第4章では「その他」として海外の法規制の動向や社内規程について解説している。重点的に解説している生成AIと著作権(Q10〜Q43)だけでなく,AI生成物の特許登録(Q44),AI生成物の意匠登録(Q49),AI生成物の商標登録(Q52)に関する法的問題についても,既存の法律の解釈に関する最新の考え方やガイドラインを示しつつ,現時点での見解を記している。 例えば特許法では,発明者は自然人でなければならないが,創作過程にどの程度関与すれば自然人の発明と認められるのかについての課題は,近年AIによる自律的創作が実現しつつあるとの指摘を踏まえ,現在も整理・検討が進行中とのことである。本書の中で繰り返し「この点の今後の議論が待たれる」,「裁判例の集積が待たれる」,「今後立法による解決が待たれる」とあり,今後議論され,法整備されるべき論点が何であるかを理解する上でも本書は非常に有益だと感じた。
本書は生成AIの急速な普及と法的な変化に対応するために,実務者が必要とする情報をわかりやすく提供している。日本の法整備が検討される中,生成AI技術の利用に関して現状どのような法的リスクが存在し,それをどのように回避するかを解説しており,今後注目すべき論点を認識する上でも,生成AIの利用を考える方にとって必読の一冊と言える。
(紹介者 会誌広報委員 H.Y)