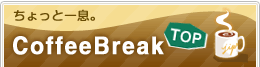新刊書紹介
新刊書紹介
インターネット・メタバースと商標の保護
権利形成から商標権侵害まで
| 編著 | 青木 博通 著 |
|---|---|
| 出版元 | 勁草書房 A5判 232p |
| 発行年月日・価格 | 2024年8月発行 3,300円(税込) |
本書『インターネット・メタバースと商標の保護』は,インターネットおよびメタバースというバーチャルな空間における商標の保護を,体系的かつ実務的に解説した一冊である。著者の青木博通先生は,知的財産法の研究と実務に精通した専門家であり,本書では,商標権侵害,権利形成,不使用取消審判,さらには他の法律による保護の可能性まで,幅広い視点から論じている。
現代社会において,インターネットは日常生活やビジネスの基盤となっており,商標の使用や侵害の形態も多様化している。一方,近年注目を集めるメタバースでは,仮想空間上のブランド展開が進む中,商標権の新たな活用が模索されている。こうした背景のもと,本書は,インターネットとメタバースという二つの空間における商標の保護を体系的に整理し,実務に役立つ知見が得られる内容となっている。
第1章では,インターネットとメタバースにおける商標の権利形成の違いを概観し,第2章では商標権侵害の要件や,それを否定するための法理を,欧米の制度も交えて紹介している。 第3章では,メタタグや検索連動型広告,ハッシュタグなど,インターネット特有の使用態様を取り上げ,豊富な判例と専門家の見解をもとに分析されている。各判決に対する著者のコメントも記載され,商標実務に不慣れな読者にとっても理解しやすい構成となっている。さらに,ドメイン名紛争(第4章),メタバースにおける商標権侵害(第5章),インターネット上での商標登録(第6章),NFTを含む権利形成(第7章)など,最新のトピックにも言及している。
また,第8章では,インターネットやメタバース上で使用される登録商標と不使用取消審判との関係について,商標の同一性,広告的使用,使用証拠など,実務上重要な論点を整理している。第9章では,商標法以外の法制度による保護の可能性として,不正競争防止法,意匠法,著作権法,民法の適用についても検討されており,仮想空間における知的財産保護の全体像を把握するうえで有用である。
本書は,裁判例だけでなく,学説や海外の動向も幅広く取り上げており,特にメタバースのように制度がまだ十分に整っていない分野については,理論を整理し,考察を加えることで,理解の手がかりを提供している。読み進めるうちに,「この場面ではどう考えるべきか」という実務上の判断のヒントが随所に盛り込まれていることに気づかされた。特に,著者のコメントが添えられた判例の紹介は,理解を深めるうえで非常に助けになった。実務に携わる者はもちろん,デジタル空間でのビジネス展開を考える読者にとっても,多くの示唆を与える一冊である。
現代社会において,インターネットは日常生活やビジネスの基盤となっており,商標の使用や侵害の形態も多様化している。一方,近年注目を集めるメタバースでは,仮想空間上のブランド展開が進む中,商標権の新たな活用が模索されている。こうした背景のもと,本書は,インターネットとメタバースという二つの空間における商標の保護を体系的に整理し,実務に役立つ知見が得られる内容となっている。
第1章では,インターネットとメタバースにおける商標の権利形成の違いを概観し,第2章では商標権侵害の要件や,それを否定するための法理を,欧米の制度も交えて紹介している。 第3章では,メタタグや検索連動型広告,ハッシュタグなど,インターネット特有の使用態様を取り上げ,豊富な判例と専門家の見解をもとに分析されている。各判決に対する著者のコメントも記載され,商標実務に不慣れな読者にとっても理解しやすい構成となっている。さらに,ドメイン名紛争(第4章),メタバースにおける商標権侵害(第5章),インターネット上での商標登録(第6章),NFTを含む権利形成(第7章)など,最新のトピックにも言及している。
また,第8章では,インターネットやメタバース上で使用される登録商標と不使用取消審判との関係について,商標の同一性,広告的使用,使用証拠など,実務上重要な論点を整理している。第9章では,商標法以外の法制度による保護の可能性として,不正競争防止法,意匠法,著作権法,民法の適用についても検討されており,仮想空間における知的財産保護の全体像を把握するうえで有用である。
本書は,裁判例だけでなく,学説や海外の動向も幅広く取り上げており,特にメタバースのように制度がまだ十分に整っていない分野については,理論を整理し,考察を加えることで,理解の手がかりを提供している。読み進めるうちに,「この場面ではどう考えるべきか」という実務上の判断のヒントが随所に盛り込まれていることに気づかされた。特に,著者のコメントが添えられた判例の紹介は,理解を深めるうえで非常に助けになった。実務に携わる者はもちろん,デジタル空間でのビジネス展開を考える読者にとっても,多くの示唆を与える一冊である。
(紹介者 会誌広報委員 Y.S)
ディープテック・スタートアップの知財・契約戦略
| 編著 | 柿沼太一 編著 大瀬佳之,奥村光平,加島広基,北原悠樹, 澤井周,竹本如洋,南野研人,森田裕 著 |
|---|---|
| 出版元 | 中央経済社 A5判 344p |
| 発行年月日・価格 | 2024年9月12日発行 4,180円(税込) |
本書は,テック系企業・スタートアップの支援に注力する柿沼弁護士が編著を務めた実務書である。長期的な研究開発と高い技術的リスクを伴いながらも,社会課題の根本的な解決を目指すディープテック・スタートアップ(以下,DTSU)の経営や成長にとって不可欠な「知財戦略」と「契約戦略」について,基本的な考え方から実務的なテクニックに至るまで,様々な具体事例を取り上げ,体系的に整理・解説された内容となっている。
本書では,DTSUの成長過程を「研究開発フェーズ」と「事業展開フェーズ」に分け,それぞれのフェーズで求められる知財・契約戦略が具体的に解説されている。
研究開発フェーズでは,コア技術の特許化が資金調達の前提条件となることが多く,研究成果の公開前に計画的な特許出願を行うことが不可欠である。特に,分割出願や優先権出願などを弁理士と連携して進めることが,将来的な機会損失を防ぐ鍵となる。また,大学や企業との共同研究においては,成果の帰属,改良発明の扱い,競合研究の制限などを契約で明確に定めることが,紛争予防に直結する。これらの論点を曖昧にしたまま進めると,上場や大型提携の障壁となるリスクが高まるため,初期段階から慎重な設計が求められる。
事業展開フェーズでは,取得した知財を活用し,ライセンスアウトやアライアンス形成,ファブレス製造など多様なビジネスモデルを構築することで,収益性と柔軟性を高めることが可能となる。契約面では,情報交換(秘密保持契約),技術検証(PoC契約),共同研究(共同研究契約),ライセンス(ライセンス契約)といった各フェーズに応じた契約設計が求められる。特に「研究成果の利用条件」「改良発明の帰属」「競合開発の禁止」などの条項は,後のトラブルを防ぐために不可欠である。
本書にはさらに,特許庁が公開するモデル契約の紹介や,契約条文例,チェックリストなども豊富に掲載されており,交渉や契約書作成の実務に直結する内容となっている。専門用語は多いものの,コラムや事例によるフォローがあるため,知財法務の専門家以外でも理解を深めやすい内容となっている。DTSUは大学・研究機関,大企業,投資家,研究者など多様なステークホルダーと長期的な関係を築く必要があるため,知財・契約の設計は法務対応にとどまらず,経営戦略そのものに直結する。知財は交渉力の源泉であり,非財務的な企業価値を示す指標にもなる。
技術力だけでは市場に認められない時代に,知財を軸に世界と対峙するための視座を提供する本書は,起業家,研究者,支援者,実務家にとって必携の一冊である。
本書では,DTSUの成長過程を「研究開発フェーズ」と「事業展開フェーズ」に分け,それぞれのフェーズで求められる知財・契約戦略が具体的に解説されている。
研究開発フェーズでは,コア技術の特許化が資金調達の前提条件となることが多く,研究成果の公開前に計画的な特許出願を行うことが不可欠である。特に,分割出願や優先権出願などを弁理士と連携して進めることが,将来的な機会損失を防ぐ鍵となる。また,大学や企業との共同研究においては,成果の帰属,改良発明の扱い,競合研究の制限などを契約で明確に定めることが,紛争予防に直結する。これらの論点を曖昧にしたまま進めると,上場や大型提携の障壁となるリスクが高まるため,初期段階から慎重な設計が求められる。
事業展開フェーズでは,取得した知財を活用し,ライセンスアウトやアライアンス形成,ファブレス製造など多様なビジネスモデルを構築することで,収益性と柔軟性を高めることが可能となる。契約面では,情報交換(秘密保持契約),技術検証(PoC契約),共同研究(共同研究契約),ライセンス(ライセンス契約)といった各フェーズに応じた契約設計が求められる。特に「研究成果の利用条件」「改良発明の帰属」「競合開発の禁止」などの条項は,後のトラブルを防ぐために不可欠である。
本書にはさらに,特許庁が公開するモデル契約の紹介や,契約条文例,チェックリストなども豊富に掲載されており,交渉や契約書作成の実務に直結する内容となっている。専門用語は多いものの,コラムや事例によるフォローがあるため,知財法務の専門家以外でも理解を深めやすい内容となっている。DTSUは大学・研究機関,大企業,投資家,研究者など多様なステークホルダーと長期的な関係を築く必要があるため,知財・契約の設計は法務対応にとどまらず,経営戦略そのものに直結する。知財は交渉力の源泉であり,非財務的な企業価値を示す指標にもなる。
技術力だけでは市場に認められない時代に,知財を軸に世界と対峙するための視座を提供する本書は,起業家,研究者,支援者,実務家にとって必携の一冊である。
(紹介者 会誌広報委員 K.A)