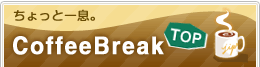新刊書紹介
新刊書紹介
企業と商標のウマい付き合い方談義
| 編著 | 友利 昴 著 |
|---|---|
| 出版元 | 発明推進協会 A5判 248p |
| 発行年月日・価格 | 2024年10月発行 2,860円(税込) |
本書は,発明推進協会の月刊誌「発明」に連載中の同名記事をベースに編纂されたものである。まえがきで「本当は企業同士でしたくてたまらなかった…(中略)…会話を,紙上で再現」と述べられている通り,全編対話形式が採用されており,著者と編集部が商標業務の現場の悩みや判断の難しさについて語っている。
企業活動において商標はブランド価値の根幹をなす重要な資産であることは言うまでもない。しかし,商標業務は特許業務に比べ発生頻度が低いことから,担当者が少なく属人的になりがちで,判断基準やテクニックといったノウハウの共有化が難しいという課題を持つ企業は少なくないと思われる。そのため「どこまで出願すべきか」や「どこまで調査すべきか」などの悩みを抱える商標担当者の姿も想像に難くない。
本書では,企業の知財業務に長年携わってきた著者が,商標実務のリアルと本質に寄り添い,現場の課題や悩みに対し,自身が蓄積してきた知識やノウハウをもとに,考え方のヒントを惜しみなく提供している。例えば「何を出願し,何を出願しないか」という線引き,「他人とカブりやすい商標」の見極め,「短期間しか使わない商標を登録すべきか」など,現場で直面する様々な疑問に対して,単にリスクを極小化することを考えるだけではなく,事業規模や使用期間,商慣習,文化,トレンド,需要者層など,各種の要素を総合的に考慮する重要性を説いている。また,商標担当者が経営層や事業部門の意向と合理的判断の間で板挟みになる状況のように,企業内で起こりがちな意思決定の現実にも鋭く切り込み,企業知財部の葛藤をユーモアも交えた軽妙な掛け合いで描写している部分など,読者は「あるある」と共感しながら,実務に役立つ知恵を身に付けられる内容となっている。
本書には,商標法や商標制度自体の解説はほとんど記載されていないが,教科書や法令集では決して学べない商標業務の現場の機微に通じたノウハウが,調査・出願・使用・トラブル対応など各種の観点から盛り込まれている。かつ,各テーマについてイメージを助けるイラストや,事例を紹介する図表も多く示されており理解しやすくなっている。そして何より,全体を通してフランクな口調(時にはタメ語)でのテンポの良い対話が読んでいて楽しい。初学者からベテランまで,商標業務に携わる幅広い層のビジネスパーソンにとって実務に役立つのみならず,仕事の合間に手に取ってリフレッシュするのにもお薦めの一冊である。
企業活動において商標はブランド価値の根幹をなす重要な資産であることは言うまでもない。しかし,商標業務は特許業務に比べ発生頻度が低いことから,担当者が少なく属人的になりがちで,判断基準やテクニックといったノウハウの共有化が難しいという課題を持つ企業は少なくないと思われる。そのため「どこまで出願すべきか」や「どこまで調査すべきか」などの悩みを抱える商標担当者の姿も想像に難くない。
本書では,企業の知財業務に長年携わってきた著者が,商標実務のリアルと本質に寄り添い,現場の課題や悩みに対し,自身が蓄積してきた知識やノウハウをもとに,考え方のヒントを惜しみなく提供している。例えば「何を出願し,何を出願しないか」という線引き,「他人とカブりやすい商標」の見極め,「短期間しか使わない商標を登録すべきか」など,現場で直面する様々な疑問に対して,単にリスクを極小化することを考えるだけではなく,事業規模や使用期間,商慣習,文化,トレンド,需要者層など,各種の要素を総合的に考慮する重要性を説いている。また,商標担当者が経営層や事業部門の意向と合理的判断の間で板挟みになる状況のように,企業内で起こりがちな意思決定の現実にも鋭く切り込み,企業知財部の葛藤をユーモアも交えた軽妙な掛け合いで描写している部分など,読者は「あるある」と共感しながら,実務に役立つ知恵を身に付けられる内容となっている。
本書には,商標法や商標制度自体の解説はほとんど記載されていないが,教科書や法令集では決して学べない商標業務の現場の機微に通じたノウハウが,調査・出願・使用・トラブル対応など各種の観点から盛り込まれている。かつ,各テーマについてイメージを助けるイラストや,事例を紹介する図表も多く示されており理解しやすくなっている。そして何より,全体を通してフランクな口調(時にはタメ語)でのテンポの良い対話が読んでいて楽しい。初学者からベテランまで,商標業務に携わる幅広い層のビジネスパーソンにとって実務に役立つのみならず,仕事の合間に手に取ってリフレッシュするのにもお薦めの一冊である。
(紹介者 会誌広報委員 H.A.)
商標実務入門〔第3版〕-ブランド戦略から権利行使まで-
| 編著 | 片山英二 監修,
阿部・井窪・片山法律事務所 編 |
|---|---|
| 出版元 | 民事法研究会 A5判 396p |
| 発行年月日・価格 | 2025年1月17日発行 4,730円(税込) |
本書は,知的財産実務の第一線で活躍する片山英二氏の監修のもと,阿部・井窪・片山法律事務所が編纂した商標実務の解説書である。2009年の初版以来,商標法の改正に即して改訂を重ねており,今回の第3版では,商標の登録要件緩和やコンセント制度などに触れつつ,近年の実務と判例の蓄積を踏まえて見直されている。
本書は,コンセプトに「商標制度の一般的な解説書ではない」とある通り,単なる商標制度の解説ではなく,実務家の視点から「ブランドの保護と活用」を体系的に解説されている点に大きな特徴がある。冒頭では「ブランドとは何か」という問いから始まり,商標法による保護制度,出願・登録に係る特許庁に対する手続実務,ブランドの管理・活用,商標権の権利行使,侵害警告を受けた場合の対応,商標法以外の保護など,実務の流れに沿って構成されている。特に後半の「ブランドの管理・活用」パート以降は,商標制度の説明を凌ぐ分量を割いており,実務家にとっての関心領域が反映されているといえる。
例えば,商標使用の社内基準の設定や,コーポレート・ブランドのグループ企業内使用,商標ライセンスに関する契約書の雛形,水際対策の具体的な手続,社内教育に関する提言など,単なる理論ではなく,実務に即した記述が随所に見られ大変参考になる。商標権の権利行使についても,単に「侵害があれば権利行使をする」といった表面的な説明ではなく,対応の選択肢とその対応の際に留意すべき点が分かりやすく整理されている。実務担当者が課題に直面した際には,まずは本書を読んだ上で対応を考えるといったことが可能である程,記載が充実しており,まさに実務上の課題解決に直結する手引書として機能する。
また,全体を通して,説明の随所に最新判例や重要判例を取り入れた構成がなされており,制度の考え方の説明と実際に問題となった事例を併せて確認でき,一体的に理解できるよう工夫されている。判例紹介は簡潔かつ要点を押さえた記述で,法律文書に不慣れな初学者にも抵抗なく読み進められる。実務で何か迷った際には関連ページを開けば,関連する判例へのアクセスができる点も,実務書としての利便性を高めている。
本書は,商標実務に携わる企業知財部門の担当者のみならず,弁護士・弁理士,企業の法務部門やマーケティング部門の担当者にとっても有益である。ブランド戦略の立案から権利行使までを実践する上で,実務上の疑問が生じた際にすぐに参照できるよう机上に常備し,日常業務の中で繰り返し活用してほしい一冊である。
本書は,コンセプトに「商標制度の一般的な解説書ではない」とある通り,単なる商標制度の解説ではなく,実務家の視点から「ブランドの保護と活用」を体系的に解説されている点に大きな特徴がある。冒頭では「ブランドとは何か」という問いから始まり,商標法による保護制度,出願・登録に係る特許庁に対する手続実務,ブランドの管理・活用,商標権の権利行使,侵害警告を受けた場合の対応,商標法以外の保護など,実務の流れに沿って構成されている。特に後半の「ブランドの管理・活用」パート以降は,商標制度の説明を凌ぐ分量を割いており,実務家にとっての関心領域が反映されているといえる。
例えば,商標使用の社内基準の設定や,コーポレート・ブランドのグループ企業内使用,商標ライセンスに関する契約書の雛形,水際対策の具体的な手続,社内教育に関する提言など,単なる理論ではなく,実務に即した記述が随所に見られ大変参考になる。商標権の権利行使についても,単に「侵害があれば権利行使をする」といった表面的な説明ではなく,対応の選択肢とその対応の際に留意すべき点が分かりやすく整理されている。実務担当者が課題に直面した際には,まずは本書を読んだ上で対応を考えるといったことが可能である程,記載が充実しており,まさに実務上の課題解決に直結する手引書として機能する。
また,全体を通して,説明の随所に最新判例や重要判例を取り入れた構成がなされており,制度の考え方の説明と実際に問題となった事例を併せて確認でき,一体的に理解できるよう工夫されている。判例紹介は簡潔かつ要点を押さえた記述で,法律文書に不慣れな初学者にも抵抗なく読み進められる。実務で何か迷った際には関連ページを開けば,関連する判例へのアクセスができる点も,実務書としての利便性を高めている。
本書は,商標実務に携わる企業知財部門の担当者のみならず,弁護士・弁理士,企業の法務部門やマーケティング部門の担当者にとっても有益である。ブランド戦略の立案から権利行使までを実践する上で,実務上の疑問が生じた際にすぐに参照できるよう机上に常備し,日常業務の中で繰り返し活用してほしい一冊である。
(紹介者 会誌広報委員 S.I)
共同研究開発契約の法律実務
| 編著 | 宇佐美善哉 編著,倉賀野伴明・鳩貝真理 著 |
|---|---|
| 出版元 | 青林書院 A5版 288p |
| 発行年月日・価格 | 2025年1月発行 4,400円(税込) |
本書は,外資系の法律事務所,製薬メーカー,医療機器メーカーに所属する3名の弁護士が共同研究開発契約の法律実務について網羅的に解説するものである。
共同研究開発契約の各条項については,英文の条項例がその対訳とともに紹介されている点で特徴がある。共同研究開発契約の和文の条項例を掲載する文献はいくつか存在するが,英文ベースのものはそれほど多くない。いわゆるオープンイノベーションが進み,外国の企業や大学との共同研究開発も当たり前になっている現在において,英文契約を軸に据えた本書は貴重である。
各条項の解説では,一般的な説明にとどまらない実務上のポイントが紹介されている。例えば共同研究開発契約において最も争点となりやすい成果帰属条項については,権利分配方法のバリエーションとともに,各当事者の費用負担額だけで権利分配のあり方を決めるべきでないといった実務的観点に触れられている。
また,各条項の解説で独占禁止法上の問題に頻繁に言及されている点も本書の特徴の一つである。共同研究開発契約については公正取引委員会が「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」を公表しているが,実務では当該指針をいかに実際の案件に当てはめるかが重要となる。本書では,競業避止義務や成果利用条項といった各条項の解説の中で独占禁止法についても説明されているほか,「共同研究開発と独占禁止法上の留意点」という独立の章を設け,米国及び欧州のガイドラインの概要にも触れながら,公正取引委員会における過去の相談事例に基づく事例検討がなされており,独占禁止法の実務感覚を養うことができるように工夫されている。
さらに,共同研究開発の当事者の立場の違いを意識した解説も見られる。例えば民間企業同士の共同研究開発と,いわゆる産学連携の取組とでは,同じ共同研究開発契約といっても実務上の留意点は異なる。本書では,「共同研究開発の相手方に応じた留意点」という項目の中でこの問題が取り上げられており,不実施補償,成果公表,贈収賄規制,費用負担といった代表的な争点について,関連する裁判例を紹介しながら,具体的に解説されている。
本書の解説対象は,共同研究開発契約それ自体にとどまらない。秘密保持契約,マテリアル・トランスファー契約,フィージビリティ・スタディ契約等,共同研究開発に関連して締結される他の契約類型についても条項例付きで解説されており,網羅性が高い。
このように,本書は類書には見られない特徴を有しており,共同研究開発契約の法律実務について基礎を学びたい人にも,新たな観点を得たい人にも,有益な一冊である。
共同研究開発契約の各条項については,英文の条項例がその対訳とともに紹介されている点で特徴がある。共同研究開発契約の和文の条項例を掲載する文献はいくつか存在するが,英文ベースのものはそれほど多くない。いわゆるオープンイノベーションが進み,外国の企業や大学との共同研究開発も当たり前になっている現在において,英文契約を軸に据えた本書は貴重である。
各条項の解説では,一般的な説明にとどまらない実務上のポイントが紹介されている。例えば共同研究開発契約において最も争点となりやすい成果帰属条項については,権利分配方法のバリエーションとともに,各当事者の費用負担額だけで権利分配のあり方を決めるべきでないといった実務的観点に触れられている。
また,各条項の解説で独占禁止法上の問題に頻繁に言及されている点も本書の特徴の一つである。共同研究開発契約については公正取引委員会が「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」を公表しているが,実務では当該指針をいかに実際の案件に当てはめるかが重要となる。本書では,競業避止義務や成果利用条項といった各条項の解説の中で独占禁止法についても説明されているほか,「共同研究開発と独占禁止法上の留意点」という独立の章を設け,米国及び欧州のガイドラインの概要にも触れながら,公正取引委員会における過去の相談事例に基づく事例検討がなされており,独占禁止法の実務感覚を養うことができるように工夫されている。
さらに,共同研究開発の当事者の立場の違いを意識した解説も見られる。例えば民間企業同士の共同研究開発と,いわゆる産学連携の取組とでは,同じ共同研究開発契約といっても実務上の留意点は異なる。本書では,「共同研究開発の相手方に応じた留意点」という項目の中でこの問題が取り上げられており,不実施補償,成果公表,贈収賄規制,費用負担といった代表的な争点について,関連する裁判例を紹介しながら,具体的に解説されている。
本書の解説対象は,共同研究開発契約それ自体にとどまらない。秘密保持契約,マテリアル・トランスファー契約,フィージビリティ・スタディ契約等,共同研究開発に関連して締結される他の契約類型についても条項例付きで解説されており,網羅性が高い。
このように,本書は類書には見られない特徴を有しており,共同研究開発契約の法律実務について基礎を学びたい人にも,新たな観点を得たい人にも,有益な一冊である。
(紹介者 会誌広報委員 T.M)