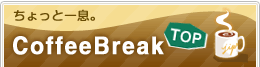新刊書紹介
新刊書紹介
知財法務を知る ― 重要テーマとその実践
| 編著 | 小泉 直樹 編 |
|---|---|
| 出版元 | 有斐閣 A5判 422p |
| 発行年月日・価格 | 2024年12月発行 4,950円(税込) |
企業の知財担当者であっても,知財と関連する法域の全てに業務として携わる方は少数派で,多くの方は主として,特許,実用新案,意匠,商標のいずれかを取り扱う業務に従事されているであろう。そして自身の担当する法域以外の情報は,意識的に獲得しにいかないと容易には得られないものではないだろうか。
本書は,有斐閣社が発行する月刊誌「ジュリスト」誌の2021年11月号から2024年2月号に掲載された連載「実践 知財法務」を,最新状況もふまえてまとめたもので,第1部を著作権,第2部を特許,第3部を不正競争・意匠・商標,第4部を特別編とし,全部で28章から構成されている。第1部から第3部では,一部の章を除き,具体的な事例をCASEとして設定し,関連する法律や過去の判決・判例を紹介,解説し,第4部では,知財経営,知財デューデリジェンス,企業内法務組織に関して論じたものとなっている。連載企画をまとめたものであることから各章独立した構成となっており,読者自身が興味を持った法域やテーマに絞って読むこともできる。
各章とも,法律上または学説上あるいは判決・判例上の解釈を整理しており,CASEを設定した章においてはそれらの整理をもとに解説がなされている。したがって,設定したCASEとは異なる場合においてもどのようなアプローチで検討を行っていけば良いのかを考える一助にもなると思われる。前述のとおり,対象CASEの検討に必要な基礎情報を整理するにあたって,その情報が示された書籍や判決・判例を挙げているので,是非注釈にも注目していただきたい。特に普段携わらない法域における重要な基礎情報や,それが掲載されている書籍等が何なのかを知ることができる点,あるいはどのようなプロセスで検討をなしていくべきかを学ぶ点でも,初学者にとって非常に良い教材である。
また,本書は著作権法に関する章が比較的割合の多くを占めている。SNSの普及もあり,近年ではコンテンツ産業以外のメーカーが独自のコンテンツを制作する事例も多く,今後もこの流れは変わらないことが予想されるが,著作権法になじみのない方々にとってコンテンツを取り扱う業界の商流等も併せて学ぶことが可能である。
第4部の最終章での総括では,知的財産分野の特徴として変化の速さを挙げている。技術の進歩に合わせた法改正が他分野に比べてほぼ最速で対応されており,またその変化は知的財産分野の複数法域に及ぶものであると評されている。本書では1冊で複数法域にわたって最新状況も踏まえた解説が行われているため,大変有益な書籍である。初学者から経験を積んだ方まで,是非お薦めしたい。
本書は,有斐閣社が発行する月刊誌「ジュリスト」誌の2021年11月号から2024年2月号に掲載された連載「実践 知財法務」を,最新状況もふまえてまとめたもので,第1部を著作権,第2部を特許,第3部を不正競争・意匠・商標,第4部を特別編とし,全部で28章から構成されている。第1部から第3部では,一部の章を除き,具体的な事例をCASEとして設定し,関連する法律や過去の判決・判例を紹介,解説し,第4部では,知財経営,知財デューデリジェンス,企業内法務組織に関して論じたものとなっている。連載企画をまとめたものであることから各章独立した構成となっており,読者自身が興味を持った法域やテーマに絞って読むこともできる。
各章とも,法律上または学説上あるいは判決・判例上の解釈を整理しており,CASEを設定した章においてはそれらの整理をもとに解説がなされている。したがって,設定したCASEとは異なる場合においてもどのようなアプローチで検討を行っていけば良いのかを考える一助にもなると思われる。前述のとおり,対象CASEの検討に必要な基礎情報を整理するにあたって,その情報が示された書籍や判決・判例を挙げているので,是非注釈にも注目していただきたい。特に普段携わらない法域における重要な基礎情報や,それが掲載されている書籍等が何なのかを知ることができる点,あるいはどのようなプロセスで検討をなしていくべきかを学ぶ点でも,初学者にとって非常に良い教材である。
また,本書は著作権法に関する章が比較的割合の多くを占めている。SNSの普及もあり,近年ではコンテンツ産業以外のメーカーが独自のコンテンツを制作する事例も多く,今後もこの流れは変わらないことが予想されるが,著作権法になじみのない方々にとってコンテンツを取り扱う業界の商流等も併せて学ぶことが可能である。
第4部の最終章での総括では,知的財産分野の特徴として変化の速さを挙げている。技術の進歩に合わせた法改正が他分野に比べてほぼ最速で対応されており,またその変化は知的財産分野の複数法域に及ぶものであると評されている。本書では1冊で複数法域にわたって最新状況も踏まえた解説が行われているため,大変有益な書籍である。初学者から経験を積んだ方まで,是非お薦めしたい。
(紹介者 会誌広報委員 K.N)
改訂版 ビジネス法体系 知的財産法
| 編著 | 田中浩之・松井佑樹 編著 |
|---|---|
| 出版元 | 第一法規 A5判 548p |
| 発行年月日・価格 | 2025年3月25日発行 7,260円(税込) |
2018年2月の初版発行から7年,その間の法改正,裁判例,学説等の動向を織り込み,改訂版である本書が出版された。本書の特徴は,端的にいえば,第一に体系(章立て)がユニークであること,第二に知的財産制度を俯瞰する実務者向けに必要十分な内容であること,そして第三に実務上重要な最新論点がコラムにまとめられていることにある。
第一の特徴であるが,一般的な知的財産法のテキストであれば,各法を順に説明する,というスタイルを採るところ,本書は,「ブランドの保護」(第2編),次いで創作物についての保護(「技術の保護」(第3編),「デザインの保護」(第4編)等)といった具合に,制度の目的や保護対象である情報の性質の違いに着目した分類を施し,各編において問題となる法を横断的に解説している。このような体系を採用することにより,眼前の問題にあたり,実務家が関連する重要な法制度をもれなく検討できるように工夫されている。例えば第1編では,商標等の保護に関し,商標法,不正競争防止法,会社法・商法,GI法等の解説に加え,冒頭の第1章で相互の制度上の違いや,その違いに応じた使い分けの実務上の指針について示しており,改めて各法の横断的・実践的な理解を深めてくれる。また,特許法からの解説ではなく,非技術系の読者が挫折しないよう,商標法から開始しているところも特徴的である。
次に第二の特徴であるが,本書は,実務において知っておくべき裁判例や審査基準を中心にバランス良く記述しており,また,よく遭遇する業界用語についても言及を怠らない。脚注で引用されている教科書や裁判例もオーソドックスなものであり,実務家が安心して読み進めることができるよう,内容が精査されている。加えて,現在も問題が生じ得るものであれば,法改正前の制度にも触れられている(例えば職務発明制度)。実務者同士の議論において必要不可欠な知識は,本書に概ねまとまっていると言って過言でない。
第三の特徴として挙げるのは,法的論点を紹介するコラムの充実度である。特に改訂版では,メタバースや生成AIに関連した最新・最先端の諸論点についての紹介が随所に散りばめられており,コラムだけを読み進めても面白い。海外で議論され,今後日本でも問題となり得る概念等(例えば「逆混同」)の紹介も見られる。こうして,本書は基礎レベルにとどまることなく,弁護士・弁理士といった専門家と専門用語を(また時には専門的な雑談をも)交えつつ事案の検討を行う場面においても,臆することのないレベルの知識を獲得することができるよう,読者を高いレベルに導いており,希有で贅沢な一冊に仕上がっている。
入門レベルを卒業した実務家にとって,是非手に取りたい一冊である。
第一の特徴であるが,一般的な知的財産法のテキストであれば,各法を順に説明する,というスタイルを採るところ,本書は,「ブランドの保護」(第2編),次いで創作物についての保護(「技術の保護」(第3編),「デザインの保護」(第4編)等)といった具合に,制度の目的や保護対象である情報の性質の違いに着目した分類を施し,各編において問題となる法を横断的に解説している。このような体系を採用することにより,眼前の問題にあたり,実務家が関連する重要な法制度をもれなく検討できるように工夫されている。例えば第1編では,商標等の保護に関し,商標法,不正競争防止法,会社法・商法,GI法等の解説に加え,冒頭の第1章で相互の制度上の違いや,その違いに応じた使い分けの実務上の指針について示しており,改めて各法の横断的・実践的な理解を深めてくれる。また,特許法からの解説ではなく,非技術系の読者が挫折しないよう,商標法から開始しているところも特徴的である。
次に第二の特徴であるが,本書は,実務において知っておくべき裁判例や審査基準を中心にバランス良く記述しており,また,よく遭遇する業界用語についても言及を怠らない。脚注で引用されている教科書や裁判例もオーソドックスなものであり,実務家が安心して読み進めることができるよう,内容が精査されている。加えて,現在も問題が生じ得るものであれば,法改正前の制度にも触れられている(例えば職務発明制度)。実務者同士の議論において必要不可欠な知識は,本書に概ねまとまっていると言って過言でない。
第三の特徴として挙げるのは,法的論点を紹介するコラムの充実度である。特に改訂版では,メタバースや生成AIに関連した最新・最先端の諸論点についての紹介が随所に散りばめられており,コラムだけを読み進めても面白い。海外で議論され,今後日本でも問題となり得る概念等(例えば「逆混同」)の紹介も見られる。こうして,本書は基礎レベルにとどまることなく,弁護士・弁理士といった専門家と専門用語を(また時には専門的な雑談をも)交えつつ事案の検討を行う場面においても,臆することのないレベルの知識を獲得することができるよう,読者を高いレベルに導いており,希有で贅沢な一冊に仕上がっている。
入門レベルを卒業した実務家にとって,是非手に取りたい一冊である。
(紹介者 会誌広報委員 K.B)
知的財産管理&戦略ハンドブック 第3版
| 編著 | 杉光一成,加藤浩一郎 編著 |
|---|---|
| 出版元 | 発明推進協会 A5判 356p |
| 発行年月日・価格 | 2025年4月発行 3,410円(税込) |
本書は,知財部のない企業,小規模な組織しか持たない中小,スタートアップ企業や大学等における知財担当者,知財に興味がある方を対象とした知財に関する法律とその管理・戦略実務の手引書である。知財業務を外部専門家にすべて任せるのではなく,社内と外部専門家で役割分担することを目指す姿としており,本書を読むことでどのように外部専門家を活用するべきか分かるようになっている。
本書は3部から構成されている。第1部は「基礎編 知的財産法の知識」である。知的財産に関する法律や制度を,実務経験が少ない人にも分かりやすいように簡潔に解説している。その他に,外国特許制度,ライセンス契約,職務発明,営業秘密等も紹介しているため,実務の広い範囲をカバーしている。
第2部は「実践編 知的財産管理」である。知財実務における管理方法や対応策が実務目線で紹介されているため,実際の実務と照らし合わせながら理解を深めることが出来る。ここでは出願管理,事業管理,紛争管理等について全部で42のテーマが掲載されているが,中でも紛争管理は,紛争実務の未経験者がイメージを得るために有用である。また,基礎的知識だけでなく,今回発売された第3版では昨今話題のAIを取り入れた知財実務も追加され,AI活用に興味がある実務者にとっても必読である。全体を通じて,企業が遭遇する機会を実例に挙げているため,知財実務者ならば一度は疑問に思ったことがあることが書かれており大変面白かった。
第3部は「実践編 知的財産戦略」である。第2部は知財のリスク管理の側面に焦点を当てており,第3部はリスク管理を超えて戦略的に知財を経営に活用する視点が入っている。知財を企業の経営戦略の中核とするために,それを担う知財部員が今後活躍するための知識とスキルは大変参考になった。なお,第3部は第3版にてテーマを約1.5倍に追加しており,IPランドスケープ,デザイン経営,国際標準化戦略,コーポレートガバナンス・コード等の最近のテーマも追加されている。
本書は,知財部のない企業等に限らず,中規模以上の企業の知財担当者が知識や実務手順を振り返るのにも適していると思われる。例えば,ルーティン化した知財業務について業務手順,業務の目的・意義を再度確認したいときや未経験の知財業務に取り掛かる前に前提知識を得たいときに該当のテーマを一読するだけで重要なポイントを押さえられる。本書は大変読みやすい手引書であるため,知財実務に取り組む上で,企業の規模や知財経験によらず,多くの知財担当者のデスクに置いていただきたい一冊である。
本書は3部から構成されている。第1部は「基礎編 知的財産法の知識」である。知的財産に関する法律や制度を,実務経験が少ない人にも分かりやすいように簡潔に解説している。その他に,外国特許制度,ライセンス契約,職務発明,営業秘密等も紹介しているため,実務の広い範囲をカバーしている。
第2部は「実践編 知的財産管理」である。知財実務における管理方法や対応策が実務目線で紹介されているため,実際の実務と照らし合わせながら理解を深めることが出来る。ここでは出願管理,事業管理,紛争管理等について全部で42のテーマが掲載されているが,中でも紛争管理は,紛争実務の未経験者がイメージを得るために有用である。また,基礎的知識だけでなく,今回発売された第3版では昨今話題のAIを取り入れた知財実務も追加され,AI活用に興味がある実務者にとっても必読である。全体を通じて,企業が遭遇する機会を実例に挙げているため,知財実務者ならば一度は疑問に思ったことがあることが書かれており大変面白かった。
第3部は「実践編 知的財産戦略」である。第2部は知財のリスク管理の側面に焦点を当てており,第3部はリスク管理を超えて戦略的に知財を経営に活用する視点が入っている。知財を企業の経営戦略の中核とするために,それを担う知財部員が今後活躍するための知識とスキルは大変参考になった。なお,第3部は第3版にてテーマを約1.5倍に追加しており,IPランドスケープ,デザイン経営,国際標準化戦略,コーポレートガバナンス・コード等の最近のテーマも追加されている。
本書は,知財部のない企業等に限らず,中規模以上の企業の知財担当者が知識や実務手順を振り返るのにも適していると思われる。例えば,ルーティン化した知財業務について業務手順,業務の目的・意義を再度確認したいときや未経験の知財業務に取り掛かる前に前提知識を得たいときに該当のテーマを一読するだけで重要なポイントを押さえられる。本書は大変読みやすい手引書であるため,知財実務に取り組む上で,企業の規模や知財経験によらず,多くの知財担当者のデスクに置いていただきたい一冊である。
(紹介者 会誌広報委員 N.K)