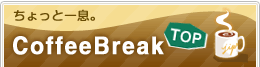������Ҳ�
������Ҳ�
��������������ꥫ���ˡ�Ȥ��μ�̳
| ���� | ����å���J��������ġ��� ����ζ���ƽ�����ƣ�¹�����¼ů�顡�� |
|---|---|
| ���Ǹ� | ͺ��Ʋ���ǡ�B5�ǡ�406p |
| ȯ��ǯ���������� | 2004ǯ12��18��ȯ�ԡ����18,900�ߡ����̡� |
�ܽ�ϡ�LexisNexis�Ҵ��ԤΡ�International��Copyright��Law������Practice������פΥ���ꥫ�Ԥ�����������ΤǤ��롣����ϲý������ҤǤ��ꡢ��ʸ�ˤ��ȥ���ꥫ���ˡ�γ�����ܺ٤˲��⤷����Ȥ���������θ���ԡ���̳�Ȥ����Ѥ���Ƥ�����ҤǤ���餷����
���⤽�����Ԥ��ܽ�������Υ������åȤȤ��������Τϡ���������ƴ֤ˤ����������������ä�ȼ�����ƹ����ˡ������̳�ȹͤ������Ȥ�ü��ȯ���Ƥ��롣�ޤ����ƹ����ˡ��ؤ�ˡ����ر����θ����Ǻ�Ȥ��Ƥ��Ŭ�Ǥ������Ȥ���θ�ˤ��Ť���
�Ĥޤ�����������Ȥϡ��ܽ��ƹ����ˡ��ؤ־�Ǵ��ܤȤ�ʤ�Ǥ����������ܹ�Ǥδ��ܽ�Ǥ��롢�Ȥ������Ȥ����㤨�Ƥߤ�����ܤΡ��õ�ˡ����סʵ�ƣ�������ˤ�θ���Ը����˱��������褦�ʤ�ΤȤ����褦�����ҤΥ�����Ȥ��Ƥϡ��ѥ����˴ؤ�����ܽ������ѥ����סʥܡ��ǥ�ϥ��������ˡ������λ��и����줿���Ǥ���а��٤��ܤˤ��줿���Ȥ����뤫�⤷��ʤ��ˤ˶ᤤ�ȻפäƤ���������дְ㤤�ʤ��Ǥ�������
���ƤȤ��Ƥϡ��ƹ����ˡ���٤�ƴ���������⤷����ΤǤ��ꡢ���ι��ܤϰʲ����̤�Ǥ��롣
- ��1�� ����
- ��2�� ������о�
- ��3�� �ݸ����
- ��4�� �����ε�°���֤Ȱ�ž
- ��5�� ����Ū��³
- ��6�� ��������ʪ���ݸ�
- ��7�� ���롦�饤��
- ��8�� �����ȵߺ�
- ��9�� ����¾���������ܸ�����
�ʾ���̤ꡢ�ܽ�Ǥ����ˡ���٤ξܺ٤����夵�줿���ƤȤʤäƤ��롣
�ܽ�β��ͤ�˲����夲�Ƥ���Τϡ���ʸ�ˤ��Ŧ�������̤ꡢ����Ƚ�㡢����Ƚ�㡢�����ƥ�������ӥ塼��¿���Ǥ��롣�ƥڡ���ʿ�Ѥ��Ƥ⤪���餯1��3���٤Ϥ������Ѥ������Ƥ���ΤǤϤʤ��������Τ褦�ʰ��ѡ����Ȥϳ��並��ˤϤ������̳�ˤ����Ƥ��ϢȽ�����ʸ���Τ뤳�Ȥ��Ǥ�����������ͭ�Ѥʤ�ΤȤʤ������Ĥޤ���ܽ�����Ȥ��ƥϥ��ѡ��ƥ����Ȥ�ǡ��ͭ��Ū�˾���礹��Τ���
�ܽ�������оݤȤʤä������2003ǯ1��15�����ߤ����ˡ�Ǥ��ꡢ����ԥ塼�����եȥ������ݸ�䥪��饤�����ӥ����ץ��Х������˴ؤ�������ʤɡ��ǿ�������ˤĤ��Ƥ�ϳ��ʤ����⤬�Ԥ��Ƥ��롣
�ʾ塢�ܽ�γ��פ��ñ�ˤ��Ҳ𤷤������ܽ��ü�������ɤ�����ν�ǤϤʤ��Ȼפ����ष����������������Ф��Ƽ���Ū�˳��Ѥ�������ˡ����Ŭ�Ǥ��������������̣�Ǽ긵�˾������Ƥ���������Ǥ��뤳�Ȥϵ����ʤ���
�ʾҲ�ԡ�����Ѱ�����������
������Ҳ�
��Ū��ޥͥ����Ȥο��������ȼ���
| ���� | ���ܡ�ľ�������� |
|---|---|
| ���Ǹ� | ���ݥꥵ������A5Ƚ��308p |
| ȯ��ǯ���������� | 2004ǯ12��15��ȯ�ԡ�4,500�ߡ����̡� |
�ܽ�ϡ�ʿ��15ǯ��MOT���೫ȯ�֥����������̤Ȥ������������ؤʤɤ���ȯ���������R��D��ά����Ū���ά�פ�˽��¤�������ΤǤ��롣
����Ȥ������Ѥ��뤳�Ȥ���Ū�Ȥ��Ƥ������Ȥ⤢�ꡢ����¿���Υǡ������Ҳ𤵤�Ƥ��롣���줬�ܽ�κ������ħ�Ǥ��롣
�ޤ������������ؤǤϹ����ͭ�ϴ�Ȥʤ�Ӥ���Ū��ޥͥ����Ȥ����Ū�ʳ�ư��Ÿ�����Ƥ���Ȥ������44�Ҥ��Ф�������Ĵ����ԤäƤ��ꡢ����ˤ�����餫�Ȥʤä��ƼҤ���Ū���ư�μ��֤��ܽ��Ż����Ƥ��롣
�������Ǻ��ͧ�ŵ������ȡ��ٻΥ����å���������������ѥ����ٻ��̡���ͧ���ؤʤɤ��κ��̳�и����Ѥ����ɮ�Կؤ����⤹�뤳�Ȥˤ�ꡢ���������̳�Ԥޤ�¿���οͤ���Ω�Ľ��ҤȤʤäƤ��롣�äˡ���Ȥˤ������κⶵ���ô������ԤˤȤäƤϳƼ�ǡ����ȼ�������1���ǤϤʤ���������
���ˡ��ܽ�ζ���Ū�����ƤˤĤ��ơ��Ҳ𤷤�����
�ܽ�ϡ��ʲ��Τ褦��6�Ϲ����ȤʤäƤ��롣
- ��1�� ����Ū�����άŪ�ޥͥ����ȡ�
- ��2�� ����Ū����ѤΥޥͥ����ȡ�
- ��3�� ����Ū��Υꥹ���ޥͥ����ȡ�
- ��4�� �ֿ�̳ȯ���Υޥͥ����ȡ�
- ��5�� ����Ū��β���ɾ���Ⱦ�����
- ��6�� �ֻ���Ϣ�Ȥ���Ū���
��1�ϤǤϡ��ӥ��ͥ���ǥ뤬¿�Ͳ����뺣�����ִ�Ȳ��ͤκ��粽�פ˹����뤿�ᡢ��Ū����ɱ�Ū���Ѥ������Ȥ��Ƥγ��Ѥء�����ˤϷбĻȤ��Ƥγ��Ѥ��������������Ƥ��뤳�Ȥ��⤫��Ƥ��롣
��2�ϤǤϡ��DZ��˻����겼����ΤǤϤʤ������ȤȤ��Ƥξ���������ä���ȯ�����ʤȤ��Ƥνи������ꤷ����ȯ�����פǤ��뤳�ȡ��ޤ������γ�ȯ���̤���Ū��Ȥ��Ƹ����������Ѥ��뤳�Ȥʤɡ�R&D��ά����Ū���ά��Ϣ�Ȥν��������⤫��Ƥ��롣
��3�ϤǤϡ���Ū��ˤޤĤ��ꥹ����ǧ����������ȥ����뤹�뤳�Ȥν������ˤĤ��ƽҤ٤��Ƥ��ꡢ��4�ϤǤϡ���̳ȯ���ؤδ�Ȥμ���ȤߤˤĤ�����Ƚ������Ȥ˲��⤬�ä����Ƥ��롣��̳ȯ��������ϼ���Ȥ�������ǡ����Ȱ�������ʾ��Ȥ����ꥹ���װ��Ȥʤ���������Ȱ��إ���ƥ��֥��åפȤ���˴�Ť���Ȳ��ͤθ���Ȥ�����άŪ�װ��Ǥ⤢�ꡢ���פ������Ǥ��롣
�����ơ���5�ϤǤϡ��������κ��ư�����̤�к�Ū���ͤȤ��Ƥ�����ɾ������Τ��ˤĤ��Ʋ��⤵��Ƥ��ꡢ��6�ϤǤϡ�����������������Ϣ�ȤˤĤ��Ƥ����Ƥ��롣
�ʾ�ΤȤ��ꡢ�ܽ�Ǥ���Ū�����¤���ݸ���ѤΥ������뤬��Ȥμ����ƾҲ𤵤�Ƥ��ꡢ����⸦���ʤɤ��礤�˳��Ѥ��뤳�Ȥ��Ǥ���ΤǤϤʤ��������Ҥλ��㡢����ô���Ԥηи���ץ饹���ȼ��δ���⸦���ʤɤ�ץ��ǥ塼�����뤳�Ȥ��ǽ��������
�ʾҲ�ԡ�����Ѱ���A��H��
������Ҳ�
������Ū�������ʪ�ʤο�ݼ������٤β���[2004ǯ������]
�������ʡ���±�Ǥ�͢���Ϥɤ�������˻ߤǤ��뤫��
| ���� | ���ܴ��Ƕ�����Ū����� |
|---|---|
| ���Ǹ� | B5�ǡ�268p |
| ȯ��ǯ���������� | ʿ��16ǯ12��ȯ�ԡ�3,000�ߡ����̡� |
������Ū�������ʪ�ʤο�ݼ�����˴ؤ���ˡ���٤���TRIPS����˴�Ť��������줿�Τ�ʿ��7ǯ�Τ��ȤǤ��롣���θ塢���ܤ�ʿ��14ǯ��ȯɽ��������Ū���ά��ˡפ�����ơ�ʿ��15ǯ���ɰ����Ը�������ʪ�ʤ�͢�������ʤؤ��ɲáɡ�
���õ��������ѿ��Ƹ����վ����ڤӰ����Ը��ˤĤ��Ƥ�͢�����߿�Ω���٤�Ƴ�����������ƤȤ��������Ψˡ�������ʲ������Ԥ�졢��ݼ�����ΰ��ؤζ��������¤��ޤ�줿��
����ˡ�ʿ��16ǯ�δ�����Ψˡ�β����ˤ�ꡢǧ���³���ϻ��˸����ԡ�͢����������������λ�̾�������Τ������٤�Ƴ�����졢Ʊǯ4��1�����ܹԤ���Ƥ��롣
�ܽ�ϡ�TRIPS����˴�Ť�������Ψˡ�����������줿�����ã�β������ȡ�ʿ��16ǯ�٤δ�����Ψˡ���β�����Ƨ�ޤ�����2003ǯ���˼���2004ǯ�����ǤǤ��ꡢ�Ǵؤˤ�����ǿ�����Ū�������ʪ�ʤο�ݼ������٤ˤĤ��Ʋ��⤵�줿��ΤǤ��롣
�ܽ��4�Ϥǹ�������Ƥ��ꡢ��1�ϡ��Ǵؤ��ȿ������ס���2�ϡ���Ū�������ʪ�ʤο�ݼ�����ס���3�ϡ�Q��A�ס���4�ϡ��Ǵؤ���Ф�����̤ε�����ˡ�ڤӻ���1ǵ��7�ȤʤäƤ��롣
�ܽ����ħ�ϡ���ݼ�����˴ط��������١���³�����ˤĤ��ơ�Q��A�����Dz��⤵��Ƥ��뤳�Ȥˤ��롣Q��A�����Ƥϡ�����Ū����γ��ספʤ����Ū�ʤ�Τ��顢���Ǵؤˤ�������Ū�������ʪ�ʤο�ݼ�����������������ס���͢�����߿�Ω�����ٵڤ�͢�����߾��������١ס���ǧ���³�ס��ֿ�Ωô�����١ס����õ�ģĹ���ո��Ȳ�ס���ǧ���³�������̴ز���������ˤޤ��ˤäƤ��롣�ʾ�Τ褦���������١���³�����Ƥ�Q��A�����Ǿܤ������⤵��Ƥ��뤳�Ȥˤ�ꡢ�ɤ߰פ����פ���ΤȤʤäƤ��롣
��̳ô���Ԥϡ�ɬ�פ˱���������Ū�����Ѥ��뤳�Ȥ���ǽ�Ǥ��ꡢ���Ѽ���Ū�Ǥ��롣
�ޤ������������Ȥ��ơ�TRIPS���ꡢ������Ψˡ�����ط�ˡ�ᡦ��ã�ξ�ʸ�䡢�Ǵ��ͼ��Ȥ��ε������Ρ�����ˡ���ǯ�δ���ˡ����ȿ����γ��פ�Ǻܤ���Ƥ��ꡢ��Ω�ľ�����������ޤ졢���ͤˤʤ�Ȼפ��롣
�ܽ�ϡ���Ū�������ʪ�ʤο�ݼ������٤�����ͭ���˳��Ѥ�����ͭ�Ѥʰ���Ǥ��롣
�ʤ���ʿ��16ǯ5����ܤ���Ū���ά���������ꤷ������Ū���ʷײ�2004�פ˱�äơ�ʿ��17ǯ��ط�ˡ��β������Ԥ���ͽ��Ǥ��롣
�ʲ���Ѱ���T.K.��
������Ҳ�
���̲����������ɻ�ˡ��ᤰ���̳Ū���������
| ���� | ������������ƽ�����¼���������Խ� |
|---|---|
| ���Ǹ� | ���ӽ�A5Ƚ��384p |
| ȯ��ǯ���������� | 2005ǯ1��25��ȯ�ԡ���� 3,300�ߡ����̡� |
�ܽ�ϡ������˾Ҳ𤹤���Ū���ʬ��Ƿи�˭��������������Ʊ�˲ơ����������ɻ�ˡ��ᤰ�������ˤĤ��ơ����ޤ��ޤʴ������顢���ߤΤʤ��ո���������̲�ε�Ͽ�Ǥ��롣
�������Ƥϡ���I�ϤΡ֤Ϥ���ˡפ���Ϥ��ޤꡢ��II�ϤΡ�2��1��1��ʼ���ɽ���˴ط��פǤϾ���ɽ�������������ˤĤ��ơ���III�ϤΡ�2��1��3��ʷ�������˴ط��פǤϾ��ʷ��֤��������������Ŭ�ʤ�����������IV�ϤΡֱĶ���̩�˴�Ϣ�����������פǤϱĶ���̩���ݸ������Ρִ������סּ����פʤɤ˹ʤ����ǡ��ո����Ҥ٤��Ƥ��롣�����ơ���V�ϤΡ��ʼ���ǧɽ���˴�Ϣ��������ס���VI�ϤΡ�»�����ס���VII�ϤΡֺ����Ÿ˾�פȵ�����³���Ƥ��롣����˲ä���ȡ����üԤ�������Ǯ���ʵ����ȵ��Ťʰո����������������κ���Ū�ʾ������ɤ�ȿ�Ǥ��줿���Ĥ�Ǥ����Ȥ��Ǥ��롣
�ʾ�Τ褦�ˡ��ܽ�ϵ��Ťʽ��ҤǤ���١���Ū��˷Ȥ�����Ǥ���С����ɤ��٤��Ǥ�������
�ڻ��üԡʽ���Ʊ����°������Ϻ��̲������ˡ�����������۸�Ρ���������ˡΧ��̳��ˡ�������ˡ��۸�Ρ���졦���ꡦ����ˡΧ��̳��ˡ��һ�������۸�Ρ��������淦���һ�ˡΧ��̳��ˡ����Ϲ��������۸�Ρ����Ϲ�������ˡΧ��̳��ˡ������½����۸�Ρ���졦���ꡦ����ˡΧ��̳��ˡ����Ĺ��ˡ��۸�Ρ�����ˡΧ�õ���̳��ˡ������ʡ��۸�Ρ��������ľ���ˡΧ��̳��ˡ����Ĺ��ҡ��۸�Ρˡ�������ҡ��۸�Ρˡ��������֡��۸�Ρ����ڡ��غ�������ˡΧ��̳��ˡ�������ͺ���۸�Ρ�����ˡΧ��̳��ˡ��������ҡ��۸�Ρ�����ˡΧ��̳��ˡ������������۸�Ρ��楢���ϥ�ˡΧ�õ���̳��ˡ������»ҡ��۸�Ρ���¼��Ʊ�õ�ˡΧ��̳��ˡ���¼���ס��۸�Ρ���¼����ˡΧ��̳��ˡ�����ľ�����۸�Ρ�����ˡΧ��̳��ˡ�������ɧ���۸�Ρ����ܡ�����������ˡΧ�õ���̳��ˡ����н�Ϻ���۸�Ρ�����ˡΧ�õ���̳��ˡ��������Żҡ��۸�Ρ�TMI����ˡΧ��̳��ˡ������Իʡ��۸�Ρ������Ի�ˡΧ��̳��ˡ��������ҡ��۸�Ρ��楢���ϥ�ˡΧ�õ���̳��ˡ��¹�ˮ�����۸�Ρ��¹�ˡΧ��̳��ˡ�������ɧ���۸�Ρ���¼��Ʊ�õ�ˡΧ��̳��ˡ��ȸ��ʻ����۸�Ρ��ȸ��õ�ˡΧ��̳��ˡ����ڹ�Ƿ�����������Ƚ��Ƚ����ˡ���¼���������������Ƚ��Ƚ���ˡ����湰�������������Ƚ��Ƚ����ˡ������ι������������Ƚ��Ƚ����ˡ��ݸ�ƻ������������Ƚ��Ƚ���ˡ���ܲ촲Ƿ�����������Ƚ��Ƚ����ˡ���ë���������������Ƚ��Ƚ����ˡ���������������Ƚ��Ƚ����ˡ��쳤���ݡ����������Ƚ��Ƚ���ˡ����ͤ��䤫�����������Ƚ��Ƚ����ˡ������õ��ҡ����������Ƚ��Ƚ���ˡ��ʰ浪�������������Ƚ��ĹȽ���ˡ��������������������Ƚ��Ƚ����ˡ���¼�̰�����������Ƚ��Ƚ���ˡ��ܺ���������������Ƚ��Ƚ����ˡ������������������Ƚ��Ƚ����ˡ�����ʹ�ҡʷ���������ˡ�����������ˡ�����ζ������������ر�ˡ̳����ʶ����ˡ������ˡʰ춶�����ر���ݴ����ά����ʶ�����
�ʾҲ�ԡ�����Ѱ����������̹���
������Ҳ�
�ƹ��õ���̳�ޥ˥奢��
��Ƚ��ȥ�����ɤˤߤ��ƹ��õ��ν��ץݥ���ȡ�
| ���� | ������� |
|---|---|
| ���Ǹ� | ����Ĵ����A5�ǡ�256p |
| ȯ��ǯ���������� | 2004ǯ12��25��ȯ�ԡ���� 2,500�ߡ����̡� |
�ܽ�ϡ��ƹ��õ����٤��¿���ο�����ǡ��ʤ�����ʿ�פ�ʸ�ϤǾܽҤ����ɽ�Ǥ��롣
��¸�Τ��̤ꡢ�ƹ��õ����٤������ˤ���Τʤ��ü�����٤ȤʤäƤ��롣��ȯ�������Ϥ��ᡢ�٥��ȥ⡼�ɳ����������̳���ҥ�ޡ��ɥ��ȥ��ʤɡ�������Ф��꤬�ʤ���
���������ƹ��ʾ�¿ȯ�θ�����Ƨ�ޤ���С��桹����κ�ô���Ԥϡʻ��Ȥ�������˶줷��ˤ��������٤���ƨ����櫓�ˤϤ����ʤ������Ȥ������ƹ��õ����٤�û���֤����Ƥ��ޤ����ȤϤǤ��ʤ���Τ���Ƭ���ˤ�����Ǥ��롣���������伫�Ȳ����ƹ��õ�ˡ���ٶ���ʤɳ��Ť������ˤ�������ܤ����ɤʤɤ����и������롣���������Ϥ����뤫�ʡ������ȸ��äƤ褤�ۤɤ˿ȤˤĤ��Ƥ��ʤ��Τ������θ����Ϥʤ������Ĥޤ�Ȥ���1�Ĥλ��¤��ͤ������롣�ƹ�ˡ�ηϡ��Ĥޤ���ƹ�ͤ�ˡΧ�ιͤ���������Ǥ��Ƥ��ʤ��Τ������ܤ����̤ޤ��õ����٤λ���������ɤ����Ȥ����Ǥ��ξ�¤���μ��Ϻ��μ�������ǡ��Ω�ä��褦���ܽ�Ϥ��Τ褦�ʻ���μ��η�������Ƥ��줿��
�ܽ�Ǥϡ��ƹ��õ������٤ˤĤ��Ƥ������ټ�ݤ��ƹ�ˡ�ηϤˤ���������դ����ܺ٤˸���Ƥ��롣�㤨�Х٥��ȥ⡼����Ϲ�ʿˡ��ιͤ���ͳ�褹�뤳�Ȥ���������롣���Τ褦�ʻ�Ŧ�ϡ������ټ�ݤ�ۤ����ƹ�ˡ�ηϤ�ʤ뺬��Ū�ʹͤ���������������ͭ�פǤ��롣ɮ�Ԥ��ƹ����������������ƹ�ˡ���Ҥ��Ƥ��ƹ�ͤιͤ�����ؤФ줿��ʪ�Ǥ��롣
�ܽ�Ϥޤ���1�Ϥˤ��ƹ��õ����٤Υ��ȥ饯���㡼�����⤵��롣����Ū�ˤ��ƹ��ˡ��Ϣˮˡ�δط��˻ϤޤꡢȽ��ˡ�ΰյ����õ���Ϳ��³���ե�������Ƚ���٤����Ū�˽Ҥ٤�졢�ɼԤ��ƹ��õ����٤�������Բķ�ʺ����μ����Ƥ���롣��2�ϤǤϿ����������������μ���Ū�õ��郎��³����3�ϤǤϼ»ܲ�ǽ���٥��ȥ⡼����Ȥ��ä����������Ū�õ��郎���⤵��롣������⺬��Ȥʤ�Ƚ����Ѥ�����ƥ��Ȥ�����Ū�˲��⤵��Ƥ��ꡢ��̳�μ��ν��Ϥˤ�äƤ����Ǥ��롣
��4�ϤǤϲ��д���³�д�Ȥ��ä��ü���õ��д����٤�����5�ϤǤ�IDS�������ʤɡ��д��μ�³�������⤵�졢³����6�ϤǤ��õ���μ�³���Ȥ��ƺ�ȯ�ԡ��ƿ������٤����⤵��롣
��������7�ϤǤϥǥ������Х�Ȥ����㳰�Ȥ��ƤΥ��ȡ��ˡ������饤����ȼ����ø�����1�Ϥ�䤤�Ƥ��ζ���ŪŬ���оݤθ��ڤȤȤ�˾ܽҤ��졢�Ǹ塢��8�ϤǤϿ����ʾ٤ˤ����륯�졼�����ˡ�������������ߡ����ץ饹���ե�������졼��γƴ�������ܺ٤˲��⤵��롣
�ɤ߽����ơ������ƹ���õ����٤�褯�������ޤ�ʿ�פˡ�����դ��פ����⤷�Ƥ��줿��Τ��Ȥ���ﴶư��Ф��롣�����٤������⤹�뤳�Ȥ��⡢��ñ���������뤳�Ȥ��������ޤ���Ȥ��ä��Ϥ��ǡ����λ�ߤ����̤���ɮ�Ԥ��������ꤿ����
�κ�������ɼԽ������Ǥ��ä��ƹ�ˡ��ؼԤˡ��ޤ����ƹ�ˡ�˾�����Υ��������������Ȥ⤳�ν���ᤷ������
�ʾҲ�ԡ�����Ѱ�����������